ある日百瀬先生がおっしゃっていました。
「研究者になるために必要なのは、いい成績よりやる気だ」と。
座学と研究では、鍛えるべき思考回路が大きく異なります。
テストでいい点数を取るためには、記憶してインプットしてアウトプットする能力が必要です。これは、小学生から多くの学生が「テスト勉強」と称してしてきたことだと思います。
一方、いい研究をするためには、効率的に実験して、実験の方向性も自分で決めて、データをプレゼン資料や論文にまとめて他人に発表して理解してもらう能力を養わなければなりません。
研究室配属される大学4年生からは、記憶力より思考力や計画性や文章構成能力やデータ解析力が必要になってきます。
いい実験をするためには、手を動かす前に頭で考えて、事前に必要な情報を論文から収集し、どのような方向性でどんな条件で何時からどの装置を立ち上げて実験するか計画し、必要な部品や薬品があれば発注して、準備を整えて実験を開始しなければなりません。
1日の限られた時間で効率的に実験するためにはどうしたらいいか、次のゼミまでにまとめておくことは何か、8月の学会で発表するためには何月までにどのデータが揃っていたらいいか、修士論文を書くためにはどのように日頃からデータをまとめていたらいいか、実験を引き継ぐ後輩のためにしておくことは何か、細かい実験道具や部品はどのように整理すれば使いやすいか、考えることは多岐にわたります。
色々な視点から物事を考察し多くのタスクをこなす必要がある研究者として活動するためには、なによりやる気が大切です。やる気は楽しいことをするためなら自然に湧いてきます。
研究室配属されてから、どれだけ早く実験に楽しさが見出せるかが重要かもしれません。
これから研究室配属される新4年生の皆様の参考になれば幸いです。
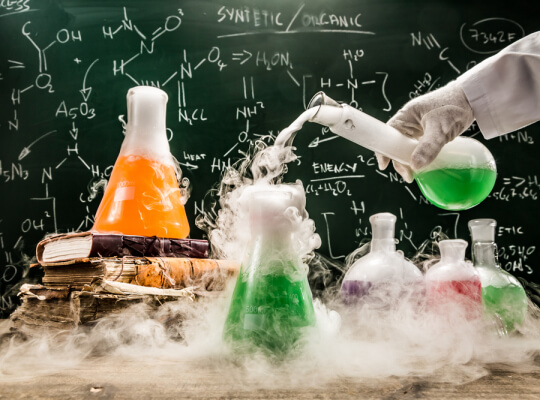
コメント
コメントを投稿